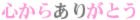小説:ボーボボ
□短篇小説置き場2
1ページ/8ページ
「実験続行不可能だな…また失敗作か」
不安な表情で見つめる"アタシ"を求める様に、此方へと震える手を伸ばして、声を出す事が叶わない口を、パクパクと5回だけ動かす"あの子"。
培養液で前髪が張りついていて、瞳は見えないけれど、小さく振戦しているその指先が全てを物語っているから、またアタシの表情は歪んでしまうのね。
"何かアタシに伝えたいの?"
"アタシ"の無言の問いに、"あの子"は微かにコクリと頷く。
そして先程と同じく"アタシ"を求める様に、右手を冷たい床から僅かに挙げて、口を動かす。
"あの子"の声はアタシに届かない。
その姿はまるで、酸素濃度が薄くなってしまった水槽の中に居る金魚の姿に似ている。
空気を送り込むポンプを動かす事も出来なくて、ただ水面で口をパクパクと動かす事しか叶わない。
ふと、濡れた黒髪の下から、うっすらと"あの子"の赤い瞳が覗いた様な…そんな気がしたけれど。
意思の疎通は叶わなかった。
"あの子"が再び、口を動かそうとしたと同時に、聞き慣れた乾いた音が一発。
培養器に容れられ、生命維持装置の管に繋がれたアタシの目の前で、成熟した花弁の様な紅が飛び散った。
ガラス越しに掛かった紅は、重力に引っ張られて細い線を描いて、一つ、また一つと下へ滴り落ちていく。
「─────っ!」
ぐらりと揺れる彼女の向こう側には、命を奪い去る鉛の玉を撃ち出す鉄の固まりを握り締めている研究員の姿。
チャリンと何かを排出したそれは、静かに銃口からユラユラと煙をたゆたわせていた。
鉛玉を受けた"あの子"は、ガクンと、力なく床へ吸い込まれる様に倒れる。
その頭部から紅の花弁を散らして。
誰かに支えられる事も無く、ただ重力に従って落ちていく。
ベシャリ、ゴツッ。
最後に聞こえてきた、頭を打ち付ける生々しい音に、"アタシ"は唇を噛んだ。
仰向けに倒れた"あの子"は、この管と機材が張り巡らせられた薄暗い"狂気"の世界の中で、一体何を知る事が出来たのだろう?
きっと、何も知る事さえ出来ずに、その短すぎる生涯の幕を下ろした。
この研究施設の外に広がる青空さえも、仰ぐ事は叶わず────
また。
まただ。
また、アタシは止められなかった。
"アタシ"と"同じ"──先程まで培養器に容れられていた"あの子"を。
躊躇せずに命を奪う研究員の手から、救い出せなかった。
また"アタシ"は"あの子"の最期を、こうやって眺める事しか出来なかったんだ…。
先程、鉛玉を撃ち込んだ研究員が、絶命した"あの子"に向かって何かをぶつぶつと呟き、露になっている白い脇腹に、硬い靴のつま先で軽く蹴りを入れる。
どうやら、息があるかどうかを試しているらしい。
ガラス越しに転がる"あの子"は、相変わらず頭部から紅い花弁を散らしたままで。
うっすらと熱を持っているであろう指先さえ、ピクリとも動かさなかった。
アタシと、遺伝子レベルが全く同じ"アタシ"の"量産型クローン"。
目の前で倒れている"あの子"は、その中の1人だった。
「検体番号〇〇〇をダストシュートへ」
蹴を入れた脇腹から爪先を離した彼が、周りにそう指示を出す。
すると、周囲に居た他の研究員達が、簡素な担架(たんか)を持ってきて、先程と変わらず床に転がったまま動かない"あの子"を乗せると。
"アタシ"の入っている培養装置からは見る事の出来ない何処か遠くへと、持って行ってしまった。
彼女は、もう此処へは帰ってこない。
何度も何度も"あの子"を見送ってきたアタシには、その事実が良く解る。
"あの子"は、命を奪われてしまったから───
これで、何度目だろう。
"アタシ"が"絶命"するのは。
これで、何度目だろう。
"あの子"が"絶命"するのは。
床に散った紅い花弁。
それは"あの子"が唯一、この世界で生きていた証となるモノなのに。
でも、それを遺す事さえ此処では許されない。
"あの子"が人生の最後に散らした赤い花弁の忘れ形見は、研究者達によってモップで乱雑にグチャグチャと拭われ。
何時の間にか、姿を消した。
「出来損ない共のデータを糧にするのでちゅ。
君だけは、何としても成功させまちゅからね」
実験の後、決まって毎回アタシの容れられている培養装置の前に来る一人の男。
培養機に飛び散った紅を拭いながら、せせら笑う"奴"は、この世界で私が一番大っ嫌いな"奴"だ。
人が死んだというのに、白々しい程に罪悪感も何もないその顔。
ああっ虫酸が走るっ!
憎い。
憎い!
こんな奴に、騙されたアタシも…憎い。
アタシが強くなる為に、"アタシ"は何回"絶命"したの?
何回、"あの子"は"絶命"したの…?
培養液に満たされた中に浮かぶアタシは何も言えず。
奴の言葉を遮断する様に、静かに瞼を閉じた───
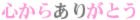
「…最悪」
やわらかいベッドに寝転がったまま、邪ティはポツリと毒付いた。
厚手のカーテンから淡く洩れる日の光が、彼女に朝を告げている。
きっと外は快晴だろうが、それとは全く真逆で、今の彼女の心境は穏やかでは無かった。
何故だろう。
培養装置から出た"あの日"から、邪ティは夢を見る様になった。
だがそれは、穏やかな物でも、ましてや年相応の少女が夢見るようなおとぎ話でも無い。
『カゲの世界』に居た頃の夢も見るものの、それはほんの一握りだ。
それは。
【うなされる様な悪夢】だった。
あの日、衝動で『カゲの世界』から飛び出した時。
右も左も解らない彼女に、ある男が「鍛えてやる」と言い寄ってきた。
行くあても無かった上、「自分自身の身体位は守れないと、この世界で生きていけない」と説得されて、彼女は彼に着いていく事にしたのだが。
それが、すべての悪夢の始まり───
辿り着いたのは、巨大な研究施設だった。
「簡単な検査をする」と言われ、促されるままに医療用の椅子に座った邪ティ。
ふと、小さな隙を見せたその白い首へ、注射器内に並々に満たされた睡眠薬を注入され、彼女の意識は其処でプツリと途絶える。
目を覚ますと、邪ティは培養液に満たされた装置の中に居た。
鼻と口には呼吸用のマスクがあてがわれ、栄養剤を流す役割を果たす生命維持装置に繋がれたその姿は、正に【籠の中の小鳥】の様である。
そして、それ以上に邪ティを苦しめたのは、彼女の目の前に広がる世界。
自分と瓜二つの少女が互いに殺し合いをし、例え勝ち残ったとしても、研究員によって処分される───それはまるで、平行世界にでも迷い込んだかの様だった。
何故ならば、この研究施設では、逃れ様の無い"最悪のシナリオ"を、繰り返し続けるのだから。
1回目の実験。
その光景に邪ティは驚き、瞳を丸くした。
なんと邪ティの目の前には、彼女と全く同じ姿形をした少女が2人、連れてこられたからだ。
何で?どうして?
何が起こってるの?
そんな彼女の精神的負荷を余所に、研究員は意気揚揚と「彼女達は、君の遺伝子情報を元に、意図的に生み出された"クローン"だ」と語った。
彼女は研究員の言葉に動揺しつつ、目の前にいる少女達を凝視する。
確かに姿形は、邪ティそのものなのだが…。
様子がおかしい。
彼女達は口をパクパクと動かすものの、"声"は一切発さないからだ。
ああ、仕方ないんだよと研究員が言葉を続ける。
それもその筈。"クローン達"は、実験の際に無意味な声を出せない様、生成する段階で、研究者の手によって声帯をアポトーシスされていたからだ。
向かい合う2人に、研究者は武器を与える。
そして、あろうことか瓜二つである互いの身体を、壊し合う様に命令したのだ。
「───!!」
やめて!!
やめさせて!!
邪ティは、実験を止させようと培養装置の強化ガラスを内側から叩いて叫ぶ。
だが、彼女の声は研究者にさえ届くこと無く、ゴボゴボと泡となって消えていった。
そうしている間にも、目の前の彼女達は、躊躇する事無くお互いの身体に武器をあてがい、傷付け合って。
そして、片方が絶命した。
「……っ」
こんなこと…!
邪ティは言葉を無くす。
ギリリと手を握り締め、瞼をきつく閉じた。
紅の花弁を纏ったクローンは、研究者へと視線を向ける。
その赤い瞳は、世界の歪みや澱みを知らないとても澄んだモノで、目の前に転がっている自分の片割れに、何が起こっているのかさえ解らない様だった。
すると、その彼女の眉間に、研究者は無言で銃を向け、鉛玉を打ち付けた。
乾いた音が響き、邪ティは驚いて、きつく閉じていた瞼を開く。
紅い花弁が、この世界に舞い散った────。
→