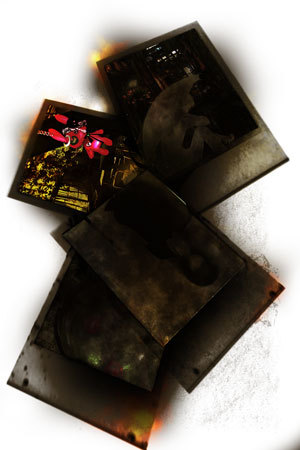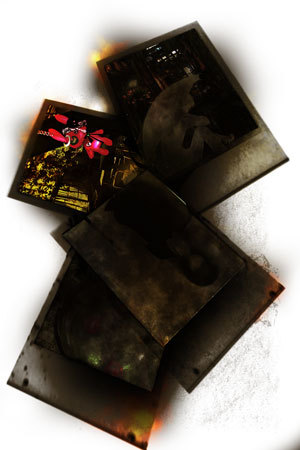......ink_3
忘れられない思い出はいつだって、色褪せないきれいな音と共にある。
その時の教室には、ひとつだけ敬遠されるようにぽつんと空いた机があった。まるで見えない結界が張られているように誰もが無意識に近づくのを躊躇うその席は、ひとりの少女のための不可侵領域だった。
彼女が教室に現れることは滅多にない。たまに現れても、ずっと机に突っ伏して寝ていたりして、まともに授業に参加しているところを見たことがない。その割には、それなりに真面目に勉強している彼と同じくらいの成績をいつも保っているのが不思議だった。
彼女が学校内で不良少女として扱われているのは皆知っていたし、何度も教師との面談に呼び出されているのも知っている。それでも彼女の態度は変わることなく、何故か留年もせずに生徒でありつづけている。その特別扱いに関する不公平感がまた、彼女への反感やあらぬ噂を生む原因になっていることを、彼は知っていた。
腰まで届くような長い飴色の髪を頭の高い所でポニーテールにして、その豊かな毛束を揺らしながらいつも胸を張って颯爽と歩いていた。化粧もピアスも染髪も校則では禁止されていたが、そんなものはどこ吹く風で、地味な紺の制服に、黒髪をきちんとまとめた生徒たちの中で、派手に着飾った少女は明らかに異質だった。
素行の悪い連中とつるんで夜な夜な遊び歩いているとか、家庭に複雑な問題があるとか、実はどこかの権力者の血縁だから好き放題にしていても許されるのだとか、色々な噂を耳にした。
そんな噂の中で唯一真実だったのは、彼女がロックバンドをしていて時々小さなライブハウスのステージに立っているということだった。
彼も、ギターケースを背負って自転車を走らせていく彼女の背中を何度か見たことがあった。安っぽい黒い布のケースには、ウサギともネズミともつかないピンク色の奇妙なマスコットがいつもぶらさがっていた。
目に痛いショッキングピンクのそれが視界に入ると、何故だか心臓が痺れるみたいに震えた。
彼女と話したことはない。同級生とはいえ、自分の名前を認識されているとも思わなかった。彼女は目立っていたからちょっとした有名人だったけれど、彼女の方は同級生にあまり興味がなさそうだった。
だから、驚いた。
きれいにグロスを塗った唇から飛び出してきた自分の名前に、彼はぽかんと間抜け面で彼女の顔を見つめた。
道端でばったり会った彼女はこれまた派手な私服姿で、背中にはいつものギターケースを背負っていた。指輪のたくさん嵌まった指先には煙草が挟まれている。慣れた仕草で煙草を燻らせる表情は、同い年とは思えないくらい大人びていて、気後れしてしまうような色気が滲み出ていた。
「君、ピアノやってるんでしょ?」
質問というよりは確信をもった様子で、不意に彼女はそんなことを言い出した。
「……なんで知ってんだ?」
「この前、表彰されてたじゃん」
「集会なんか出てたのか」
「たまたまね」
確かに、数週間前、コンクールで受賞したことを集会で表彰されたことがあった。
どうして彼女が話しかけてきたのか、どうしてピアノの話なんか振って来たのか、戸惑ってぎこちなく受け答えする彼の様子を、彼女は面白そうに眺めていた。
「ピアノ上手いよね」
「……聴いたことあんの?」
「君の家の近くを通ったら、いつも聴こえてくる」
「家、近所なの?」
「ううん。聴きたくなった時に、聴きに行くの」
「……え?」
彼は困惑した。話したこともない有名人の彼女が、わざわざ彼の練習の音漏れを聴きに自宅の近くまで足を運んでいたとは。
「ストーカー……?」
「そういう言い方しないでよ。失礼だな」
少し気まずそうに口を尖らせて抗議する表情は、さっきまでの余裕のある態度とは違って、年相応の少女のそれに見えた。
「ピアノ、ずっとやってるの?」
強引に話の流れを戻そうとするのに逆らわず、彼は頷いた。
両親が現役で音楽を生業としている人たちだから、生まれた時から音楽は常に傍にあった。物心ついたときから楽器に触れて生きてきた。
「英才教育ってやつ?」
「まあ、そんなもん」
将来自分もそういう方面に進むのか、それとも別の道に進むのか、それはまだ決めかねていた。もうそろそろ真剣に考え、決断しなければならない時期だ。両親は音楽の道に進んで行って欲しいと思っているのは何となく空気で感じている。だが、いくら周囲に才能があると褒められても、自分自身でそれを実感できないでいた。
「すごいなあ。私には全然わからない世界だ」
わからない世界にいるのはそっちの方だと、彼女の顔を見て思う。まるで自分とは違う時空を生きる異邦人のような彼女に褒められるのは、何とも言えずくすぐったかった。
「あんたも、音楽してるんだって?」
「うん。そうだよ。知ってるんだ」
「噂で聞いた」
「そっか。じゃあ、今度、聴きに来てみない?」
そうして彼が初めて触れたそれは、今まで聴いたことのない音楽。自分の『人間』の姿を壊す音楽だった。それは、モノクロームの風景を極彩色で塗り潰すような、鮮烈な音だった。
......